最大10連休のゴールデンウィークが終わり、連休ムードが落ち着いた時期になりました。ゆっくりと過ごされた方は、仕事モードへの切り替えが大変かもしれませんね(笑)僕にとって連休中は製作に集中するには絶好のタイミングで、遅れを取りもどずべく製作に集中できました。ですが少々、引き篭もり過ぎてしまって、また生活のリズムがまたまた夜型に変わってしまいました、、、f^^;
来週末には、台東区界隈で開催される「ものづくりで町おこし」を目的とした毎年恒例のイベント「モノマチ11」が控えておりまして、しばらくこのままのリズムが続きそうです。※無二としては、5月25日(土)、26日(日)に無二製品の受注会を行う予定です。詳細は、また改めてご案内させて頂きます。
少し話が逸れてしまいましたが、、、ゴールデンウィーク中の製作の合間に、以前から気になっていたセイコーミュージアム(旧セイコー時計資料館)に行くことができました。※セイコーミュージアムは1981年にセイコーの100周年記念事業として時と時計の研究資料の収集・保存の目的のために設立された資料館です。
小さい頃から時計が好きで、セイコーの時計もいくつか持っていますが、実際にセイコーの歴史に触れた事がなければ、「時」と言う部分に関しても深く追いかけた事が無く、今回のセイコーミュージアム訪問はとても刺激的でした。
全部を書くことは難しいですが、同じように時計、セイコーに興味のある皆さんとの情報共有に繋がれば幸いです〜
セイコーのミュージアムなので、セイコーの歴史だけだと思っていたら、古代の日時計から水、火、砂、機械式時計、クオーツ時計へと発展してきた時を計る道具であった時代から見ることができたのはとても意外でしたし、まだ時間の概念がない時代に計りの道具として使われていた歴史に触れられた事はとても勉強になりました。
世界最古の機械式時計と同じタイプの鉄枠塔時計は1500年頃のもの。
その当時、一日30分から1時間の誤差があったという事ですが、重りの重力で歯車が回る様子は、500年以上も前の時代に考えられたものとは思えなかったです。動力を伝える仕組みを考えた人の凄さを感じました。
重りが下に下がるスピードを既にその時代に歯車でコントロールしていたなんてビックリでした。
フロア1階では、古来の時の計測から時計へと進化してきた流れを見ることができます。その中の一つに木箱にセッティングされた時計があり、船に時計を載せるために作られた船舶用時計(マリンクロノメーター)でした。よく目にする壁掛けタイプではなく、木箱にセッティングされ、船が揺れても水平を保ち、狂いにくい構造になっているそうです。時計の文字盤は直径15cmくらいでしょうか?ユリスナルダンの同じタイプとセイコーのものが並んで展示されていましたが、とてもカッコ良かったです♪
ヨーロッパの懐中時計がいくつも展示されていて、そのどれもが彫りや装飾が豪華に施されている、当時の高貴な雰囲気を感じました。
フロア2階では、セイコーの歴史はもちろん、江戸時代に使われていた和時計、セイコーウォッチ、ローレル、クォーツアストロン、プロフェッショナルダイバー、そしてグランドセイコーまで見応えあります。一つ一つ掘り下げて描くには時間が足りませんf^^;
グランドセイコーに関しては、実際に時計に使っているとても小さいパーツも見ることができます。その中でも、髪の毛よりも細い一本の線パーツを渦巻き状に仕上げて作られるヒゲゼンマイはとても美しかったです。
本当に時間が足りません。。。
セイコーミュージアムのHPでも解説が聞ける様になっていますので、気になる方は是非HPもチェックしてみて下さい♪
セイコーミュージアム→ https://museum.seiko.co.jp
僕もまだまだこれから時計の事について勉強していきたいと思います!
早速、、、新しくSEIKOウォッチコレクションを追加しました〜
また、今回の訪問は同行させて頂きました方のご好意で、セイコーインスツル(株)で活躍されていた「村上斉」さんに館内の案内をしていただけ、とても有意義な時間を過ごさせて頂きましたm(_ _)m また訪問したいと思います。
中途半端で申し訳ありませんがf^^;
時計の事については、また書きたいと思います♪Thank you!
コードバンレザーブランド「無二」
主宰 宮崎泰二***価格改定予定のお知らせ***
「無二/Muni」ブランド立ち上げより据え置き価格にて昨今の材料費、運送費コストの高騰を吸収するべく努力を重ねてまいりましたが、現在のままでは吸収しきれなく、大変厳しい状況となっております。
つきましては、品質の維持・向上に努めながら、7月1日受注分より商品の価格を改定させて頂きたく思います。
新価格につきましては、現在調整中でございます。決まり次第、改めてお知らせさせて頂きます。価格改定は心苦しいお知らせとなりますが、今後も良質素材としっかりとした製品づくりを継続し、皆様にご満足いただける製品の提供に努めてまいりたいと思っております。
何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
***価格改定予定のお知らせ***





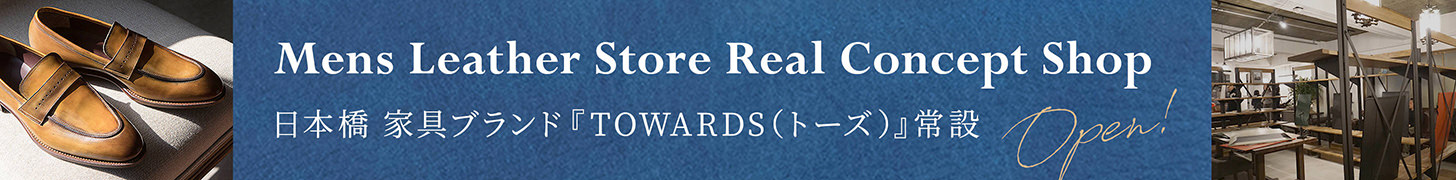

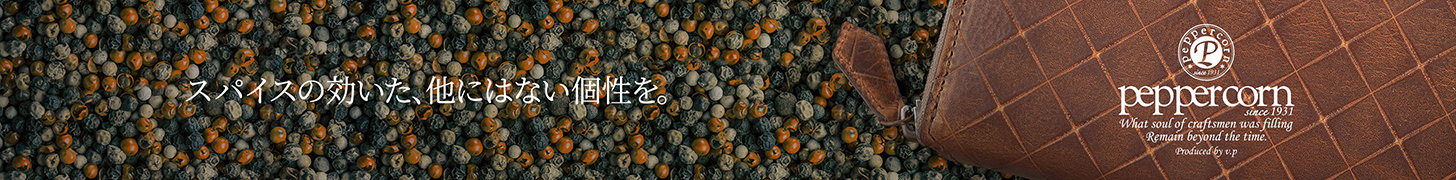



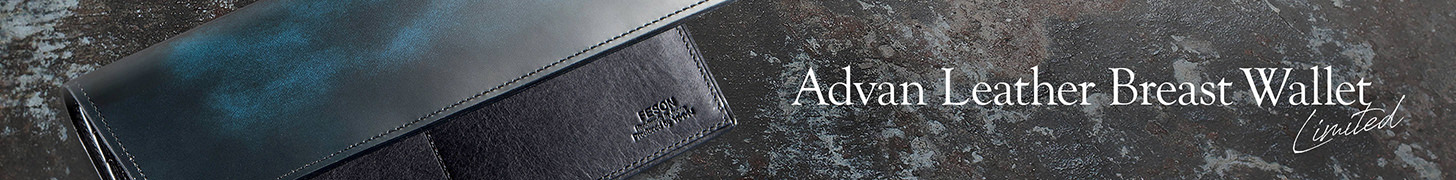







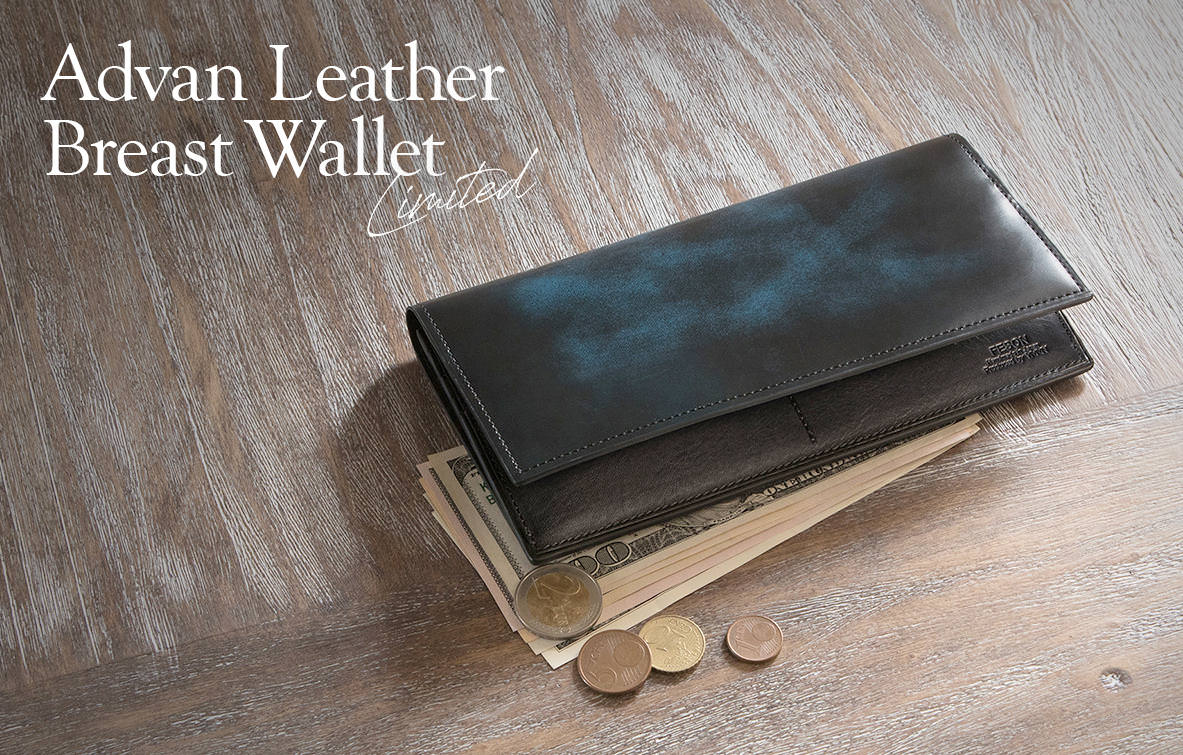



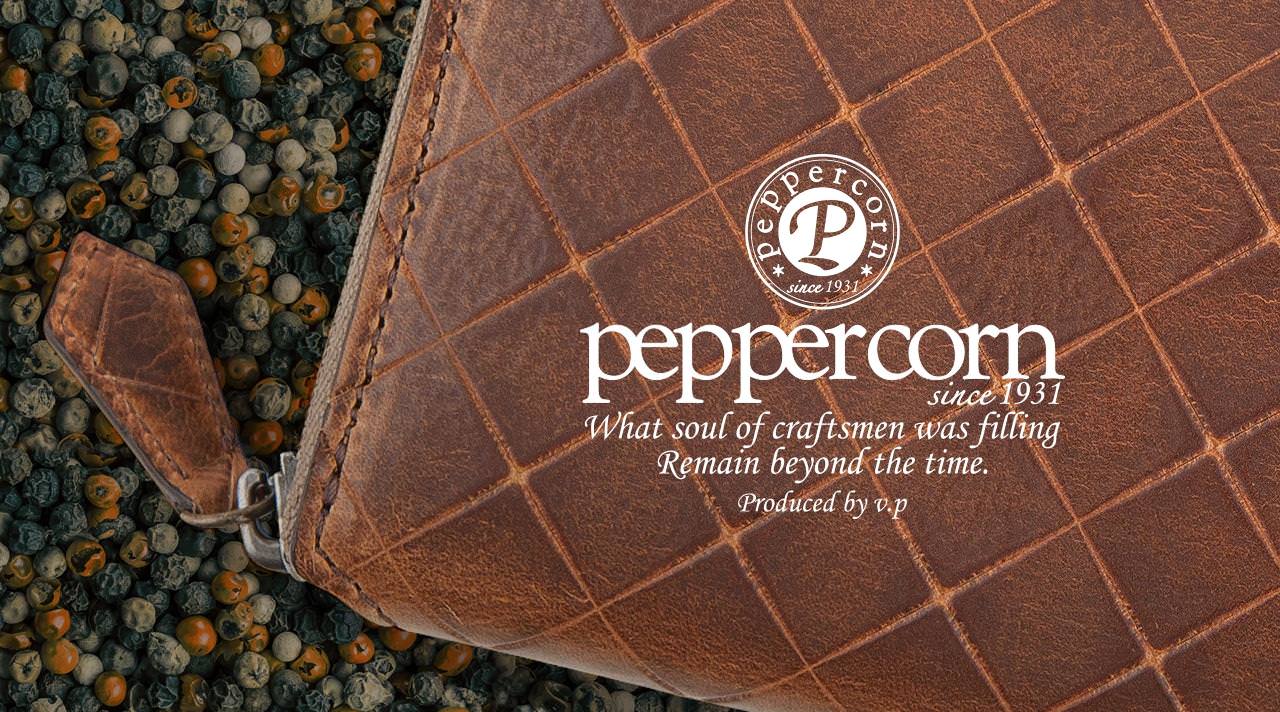

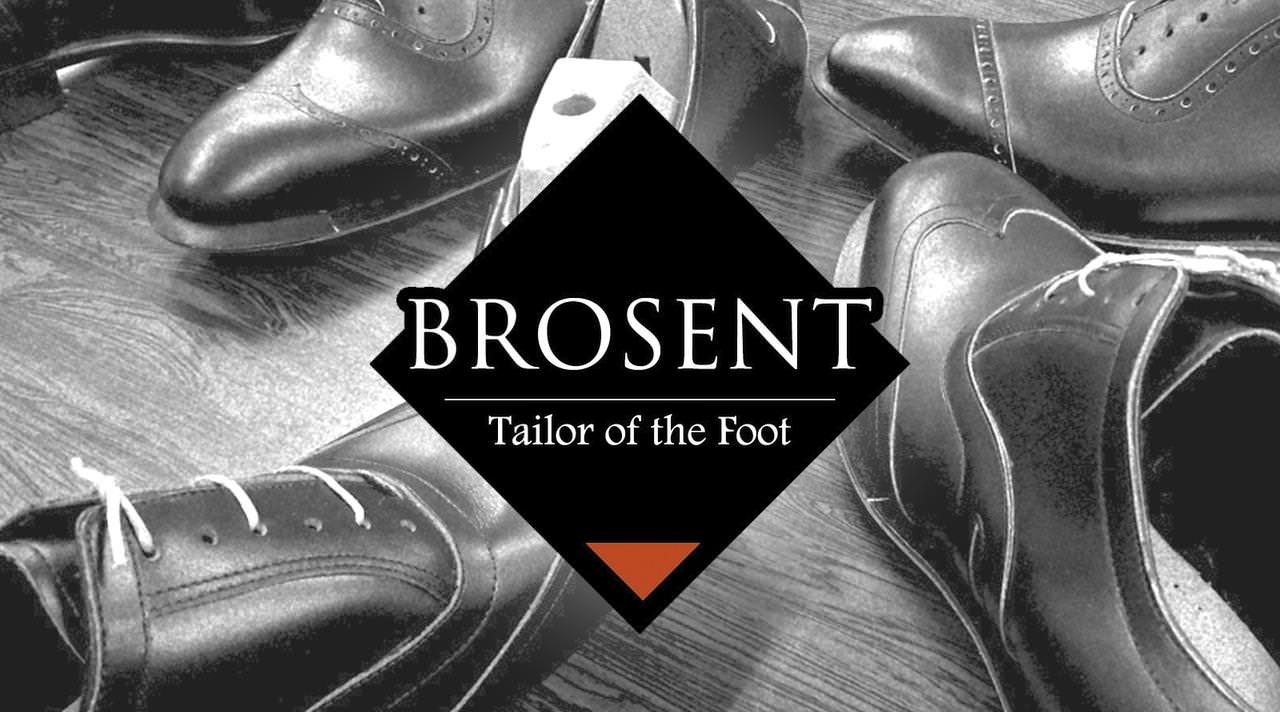

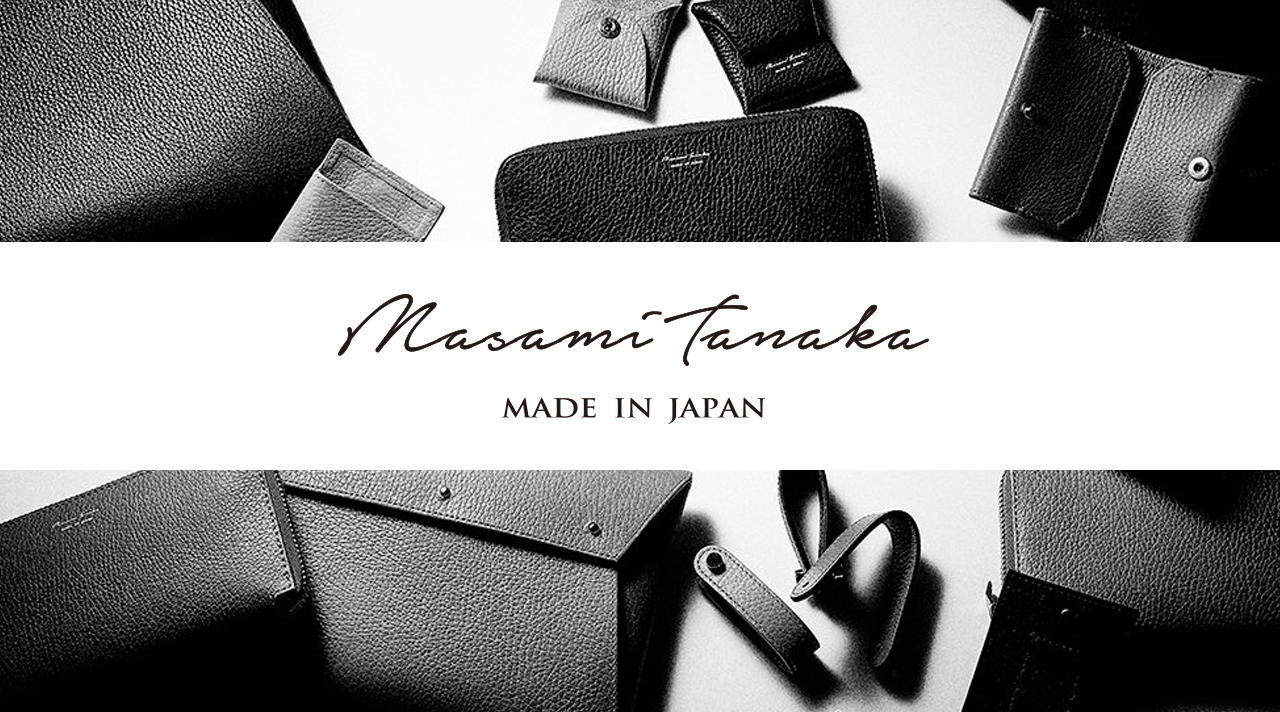


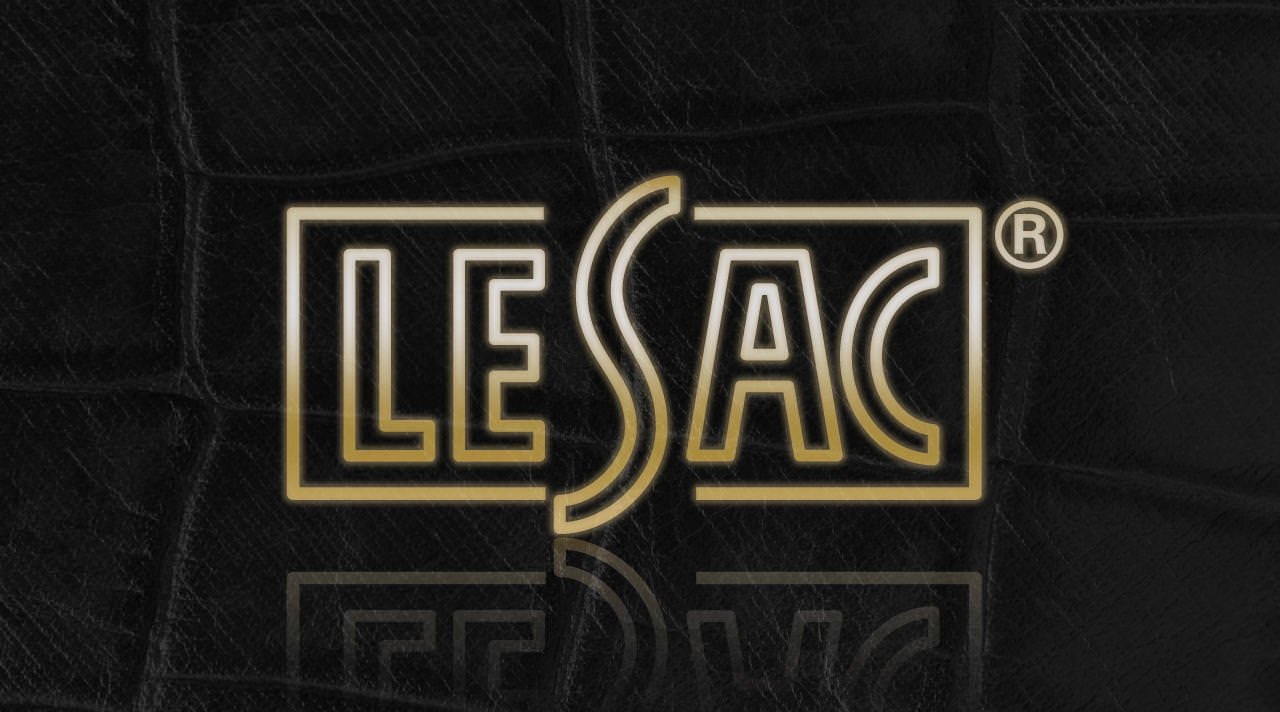
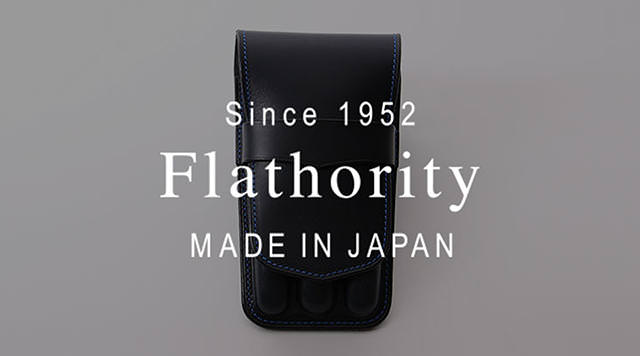
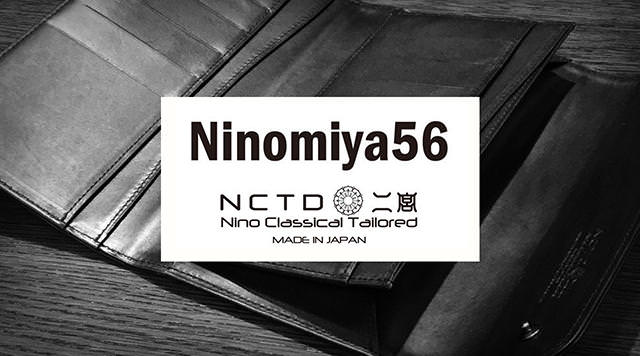


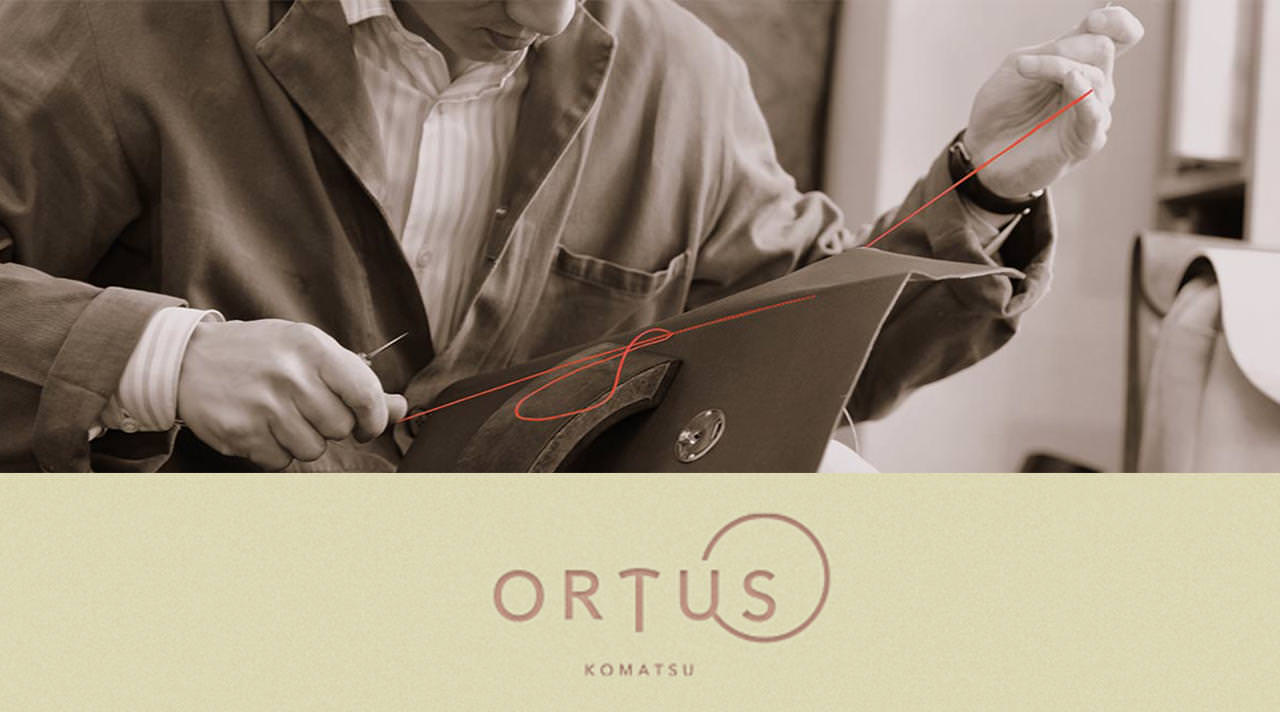



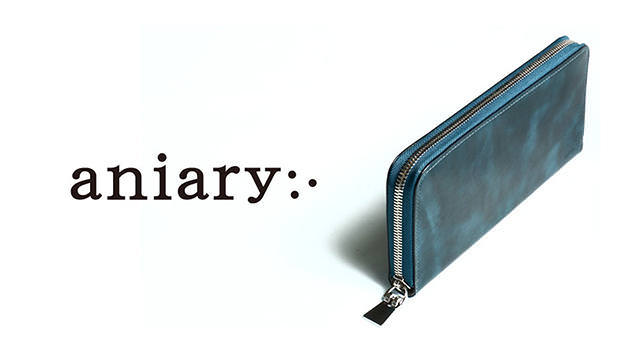

View Comment
0